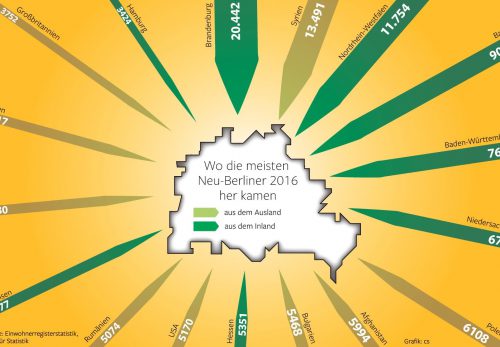ベルリン国際映画祭が開催

「2018年ベルリン国際映画祭」ポスター(公式Twitterより)
2/15~25の10日間、世界三大映画祭のひとつである「ベルリン国際映画祭(Berlinale)」が開催された。エキサイティングでコスモポリタンな文化の中心地であるベルリン、その抜群な多様性のセンスはベルリンを「映画の街」としても特徴づける。公式HPによると、ベルリン国際映画祭でのチケット売り上げ枚数は33.4万枚を超え、127の国と地域から約21,000人の映画関係者、約3,700名の報道陣が集まるそう。期間中は世界中から集まった約400本の映画が紹介されていく。「文化・アートのメッカ、ベルリン」のパワーが映画を通し世界中に共鳴する10日間、日本にもその熱気は伝わってきている。
映画とベルリンの関係性は?
なぜこのように映画とベルリンが深い関係にあるのだろうか?その理由は、「黄金の20年代」と呼ばれる1920年代の文化開花にまでさかのぼる。
1918年、ドイツ帝国の降伏をもって第一次世界大戦が幕を閉じた。これと同時に「ヴァイマール共和国(ドイツ共和国)」が誕生し、ベルリンでも新しい都市の姿が模索されるようになった。これを受け1920年「新しい都市自治体ベルリンの創設に関する法律」が発効され、「大ベルリン(Groß Berlin)」が成立した。これによりベルリンは、全20区・面積約900㎢(ロサンゼルスに次ぐ当時世界第2位)、総人口380万人(ロンドン、ニューヨークに次ぐ当時世界第3位)を擁する近代的大都市となったのである。この勢いと戦後のインフレーションを受けながら、ベルリンは「黄金の20年代(Golden 20’s)」と呼ばれる文化開花時代を迎えた。
この時代は、ベルリンの経済復興に目を付け各国から集まった富裕層・文化人・芸術家たちがメインアクターとなり、映画館・キャバレー・高級商業施設がベルリン西部のツォー駅(Zoologischer Garten)やクルフュステンダム通りに軒を連ねたのである。ベルリンの市域が広がり、フリードリヒ通り(Friedrich Straße)やウンテル・デン・リンデン(Unter den Linden)に続く中心地が必要とされていたため、ツォー駅およびクーダム付近は副都心としての役割も担いながら、対外的・閉鎖的な「田舎のベルリン」というイメージを一新させる拠点となった。こうして「黄金の20年代」は開放的な文化の結節点として、世界を牽引するベルリンを生み出していったのである。ベルリン国際映画祭は1951年に始まったものだが、西と東という対立軸が存在し始めた時代の中で、黄金の20年代から育ってきた西側の文化や芸術を東側へ誇示していきたいというメッセージがあったのではないかと考えられる。
ポツダムも映画と縁が深い

Studio Babelsberg外観http://wikimapia.org/1191576/Studio-Babelsberg

Studio Babelsberg正門
ベルリンの隣に位置するポツダムも、映画との縁がある。バーベルスベルク(Barbelsberg))にある映画製作所はその最たる例だ。ベルリンが映画を「観る」ことの聖地なら、ポツダムは映画を「撮る」ことの聖地と言えるだろう。バーベルスベルクスタジオは1912年に設立された世界最古にして最大の映画撮影スタジオであり、またヨーロッパのサービスプロバイダーを牽引する立場として様々な映画・映像・広告制作などに取り組んでいる。今日までの映画史はこのスタジオの歴史であると言っても過言ではなく、ここから日々名作が誕生しているのである。
文化・芸術産業が街にもたらすもの
ベルリン・ポツダムは度重なる破壊と更新を繰り返した世界史の中心的な場所である。そのような背景から、このエリアには地方分権の進むドイツにおいて長い間中心産業が育ってこなかった。旧東ドイツに位置しており、旧西ドイツの「強い工業」的特性を持つ州に対し戦後は圧倒的な差をつけられていた。しかしながら、このような歴史を辿ってきたからこそ、現在は映画のような文化・芸術産業がしっかりと地に根を張り、豊かに葉を付けるための土壌が育ってきたと言えるのではないだろうか。ドイツ全体に産業構造転換が起こり、ドイツ国内の様々な都市で代替産業が模索されているが、例えばベルリンやポツダムほど映画産業が根付く場所はないだろう。映画を作り、観るまでの環境が整っているベルリンとポツダムにおける益々の協働が期待される。